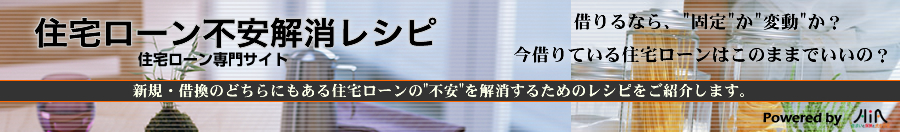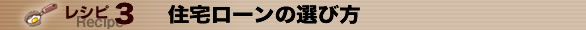
 返済額の内訳のカラクリとは? 返済額の内訳のカラクリとは?
すでに住宅ローン返済中の皆様はご存じのはずですが、
返済を開始すると、
『返済予定表(ヘンサイヨテイヒョウ)』
なり『償還表(ショウカンヒョウ)』が送られてきていると思います。
そこには何が書かれているか、覚えていらっしゃいますか?
そう、1.返済額、2.元金、3.利息、4、借入残高、です。
この書類を見ると、毎回の『ヘンサイガク』がいくらで、
そのうち『ガンキン』返済分と『リソク』分がいくらずつで、
『ザンダカ』がどのくらいの割合で減っていくかがわかります。
《固定特約付ローン》の方は、固定期間中の内容が出ており、
《全期間固定ローン》の方は、全期間の内容が出ています。
すなわち、35年返済で組んだ方は、35年分(毎月分420回、
ボーナス分70回)の内容の明細が、ご親切に延々と書かれています。
これをご覧になって、
Aさん:「さあ、完済めざしてがんばるぞー!」
――→ モチベーションが高くて、立派な方だと尊敬します。
Bさん:「こんなに長いんだなぁ、うんざりするなぁ」
――→ ごく普通の感覚の方だと同情します。
Cさん:「そんなの来てたっけ? どっかにしまったような?」
――→ 今回はいい機会です、後悔しないように再確認しましょう。
さて、皆さんAさん、Bさん、Cさん、どのタイプでしょう?
ちなみに、私も最初は、BさんとCさんの中間ぐらいでした。
これから、ローンを組む方は、決してCさんには
ならないようにしましょう。
◇◆◆
◆◇◇ ローンの返済額の内訳はいつわかるの?
◇◇◆
住宅ローンを組んでいる方は、当時を思いおこしてください。
元金と利息の内訳 を知ったのは、
住宅購入においてどの時点だったでしょう?
おそらく『住宅を購入する契約前にわかっていた』
という方は少ないと思われます。
通常、販売側では住宅ローンに関して、
このような詳細までは伝えません。
金融機関の窓口でも、毎回の返済額の確認にとどまり、
そこから先の詳細は、説明なしのようです。
ショウカンヒョウが送られてきて、
はじめて知るというのがむしろ普通なんですね。
しかし、よく考えてみましょう。
これから、大きな金額を借入して、長い期間返済しつづけていく
ローンです。どれを選ぶのかは、慎重に検討して選択したい
という方が多いはずです。
事実、私のところに住宅ローン相談に訪れる方々は、
『はじめて、返済額の内訳を見た!』という方ばかりです。
ということは、どんな内容の返済をしていくのかを知らずに、
ローンを選択している方がほとんどであるということです。
今回の講座では、この点をクリアにします。
◆◇ ◆
◆◇ 金利別に内訳を検証
では、金利別にシミュレーションしたものを見てみましょう。
借入条件は、元利均等返済で、
2000万円を35年返済で組んだ場合の設定です。
ボーナス返済はなしで、毎月返済のみと仮定します。
○ケース1
金利1%の場合
毎月返済額:56,457円
元金返済分:39,790円
利息返済分:16,667円(毎月返済額の約29.5%)
 ̄ ̄ ̄ ̄
○ケース2
金利2%の場合
毎月返済額:66,253円
元金返済分:32,919円
利息返済分:33,333円(毎月返済額の約50.3%)
 ̄ ̄ ̄ ̄
○ケース3
金利3%の場合
毎月返済額:76,970円
元金返済分:26,970円
利息返済分:50,000円(毎月返済額の約64.9%)
 ̄ ̄ ̄ ̄
○ケース4
金利4%の場合
毎月返済額:88,555円
元金返済分:21,888円
利息返済分:66,667円(毎月返済額の約75.2%)
 ̄ ̄ ̄ ̄
返済開始時は、上記の内訳となります。
もちろん、変動、固定など条件の違いはあるものの
1%も4%も実在しているローンの金利です。
とても同じ金額を借りたものとは、思えないような違いですね。
◆◇ ◆
◆◇ 返済期間を修正して内訳を検証
先ほどのシミュレーションに返済期間を修正したものを見てみましょう。
借入条件は、2000万円を20年返済で組んだ場合の設定です。
ボーナス返済はなしで、毎月返済のみと仮定します。
○ケース5
金利1%の場合
毎月返済額:91,979円
元金返済分:75,312円
利息返済分:16,667円(毎月返済額の約18.1%)
 ̄ ̄ ̄ ̄
○ケース6
金利2%の場合
毎月返済額:101,177円
元金返済分:67,843円
利息返済分:33,333円(毎月返済額の約32.9%)
 ̄ ̄ ̄ ̄
○ケース7
金利3%の場合
毎月返済額:110,920円
元金返済分:60,920円
利息返済分:50,000円(毎月返済額の約45.0%)
 ̄ ̄ ̄ ̄
○ケース8
金利4%の場合
毎月返済額:121,196円
元金返済分:54,529円
利息返済分:66,667円(毎月返済額の約55.0%)
 ̄ ̄ ̄ ̄
ご覧のように、元金返済分の割合が上がります。
また、もうひとつ注目していただきたい点があります。
鋭い読者の皆さまなら、お気づきになったと思いますが、
利息返済分は、変わらない という点です。
すなわち、返済開始2ヶ月目以降の利息分の減りが多くなる
ということがわかります。
以上8つのケースで見てみましたが、
ご自身がどのケースに当てはまるのか、あるいは近いのかを、
再度、確認してみましょう。
◇◆◆
◆◇◇ ケーススタディーの結果を踏まえて
◇◇◆
今回のシミュレーションの中で、
もっとも利息返済分の割合が大きいのは、ケース4です。
じつに75%を超えます。
一方、もっとも利息返済分の割合が小さいのは、
ケース5で、その割合は、18%です。
1%のローンは、民間住宅ローンのキャンペーン商品の類です。
ずっと1%ではありません。金利上昇のリスクがあり、
どこまで金利があがるのかは、わかりません。
4%のローンは、住宅金融公庫で設定した11年目以降の
金利です。こちらは、4%を超えることはありません。
金利上昇リスクはデメリットです。
リスクを含むローンの低金利のメリットとは、このように【一定期間、
きわめて低い金利負担】である状況を意味するということです。
一方、金利上昇リスクがないことは、
大きなメリットであると同時に、
『ローン返済当初から
それなりに大きい金利負担をしていく』
ことを意味します。
ですから、一概に
「固定金利の方が良い」
とは言い切れません。
金利上昇リスクがあるからソン、ないからトクと考える前に、
元金、利息の割合まで考慮して判断することをおすすめします。
|