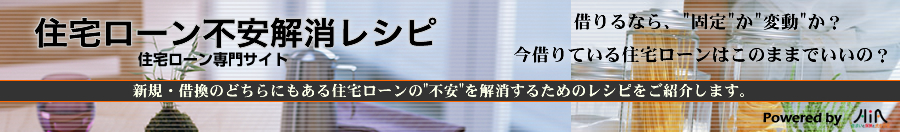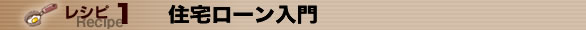
 ヘンサイヒリツ、ユウシヒリツとは何者だ! ヘンサイヒリツ、ユウシヒリツとは何者だ!
先日、あるお店で、
『3,000円以上お買い上げの方に消費税分還元!』
というセールをやっているのを見かけました。
これは店側が3,000円以上、買物をした方に限りメリットを提供するもので、
お店にとって好ましい「特定の条件」にあてはまるお客様を選んでいると
いうことになります。
ヘンサイヒリツ、ユウシヒリツも
この「特定の条件」に通じるものです。
実は、金融機関も好ましいお客様を
選んでいるって知ってました?
最初に、ヘンサイヒリツ、ユウシヒリツを
ご存じでない方のためにカンタンにお話しします。
返済比率(返済負担率ともいいます)および融資比率は、
金融機関がお金を貸すためのひとつの基準です。
返済比率は、「税込年収」に占める「ローン返済額(年間)」の割合です。
融資比率は「物件価格」に対する「借入れ」の割合です。
借りる側の個人から見ると、
借りるための必要条件の1つということになります。
◆◇ ◆
◆◇ サラリーマンの田中さんはローンを借りられるか?
では、具体例をあげてシミュレーションしてみましょう。
【設定】
サラリーマンの田中さん(39歳)
年収600万円(税込)
借入希望3000万円(M銀行)
返済比率35%
この田中さんの場合では、
年収600万円×返済比率35%=年間返済の上限210万円
となります。
【ケース】
田中さんは60歳の定年退職の前にローンを完済したいと考え、
5年間固定の1.5%の住宅ローンを20年返済で組むことにしました。
年間返済額は174万円弱ですが、今なら奥さんもパートで
働いているので十分やっていける、問題ないと踏んでいました。
ところが、これなら銀行も通ると思いきや実は通りません。
なぜなのでしょうか?
【種あかし】
確かに 年間返済額 174万円 > 210万円 で基準の範囲内ですが、
実は銀行が計算する場合の金利は
1.5%ではなく、4%なのです。
4%で計算した年間返済額は218万円強です。
つまり 年間返済額 218万円 < 210万円
となり、上限オーバーです。
田中さんがこの基準をクリアするためには、
(1)20年返済を変えずに借入額を2880万円に落とす
(2)22年返済に延ばして3000万円を借入する
の選択を迫られることになります。
普通なら借入額を落とすと住宅が買えなくなるので
(2)を選ぶしかないという方がほとんどです。
あなたが田中さんでも、しぶしぶそうしますよね。
◆◇ ◆
◆◇ ヘンサイヒリツだけで安心してはいけない!
では、なぜ銀行の計算は4%なのでしょう?
理由は、今でこそ長いこと低金利ですが、過去に
さかのぼれば住宅ローンの金利は平均で4%以上になります。
また、金利が上昇した場合に借りた人が返済不能になる
リスクを避けるためでもあります。
つまり、金利が4%になるまでは安心ということでしょうか?
必ずしもそうとはいえません。
では、注意が必要だとしたらどんな点でしょう。
ここでは3つ挙げます。
1つは「ヘンサイヒリツ」が税込年収に対する比率である点です。
世帯によって家族構成は異なります。すなわち支出も貯蓄額も異なります。
しかし、ローンを組むにあたっての基準には
支出や貯蓄額までは考慮されません。
どんな家族構成でも一律で見ている点は安心とはいえないので、
それぞれの家庭に即した判断が必要になります。
2つめは税金や社会保険料の負担が増えた場合です。
昨今、さまざまな制度改正がめまぐるしく行われています。
税率が変わり税負担が増えたり、年金や健康保険の保険料が
増えれば、それだけ手元に残るお金が減ることになります。
3つ目はインフレになった場合です。
インフレになると通常は金利が上がり、
変動金利で組んだ住宅ローンは返済額が増えます。
しかし、増えるのは返済額だけではありません。
インフレになるとモノの値段も上がります。
つまり、支出額が全体的に増えるということになります。
普通はインフレ時には収入も増えるものですが、
もし収入だけが上がらないなどということがあると
大変なことになってしまいます。
返済比率の基準は、フラット35、財形、銀行でそれぞれ異なります。
また、計算する際の金利も銀行によっては4%ではないところもあります。
返済比率ギリギリの住宅ローンを組む時は、勇気と注意と
対応策が必要になるということを知っておきましょう。
最後に返済比率、融資比率における審査基準の目安を書いておきます。
・返済比率
25%まで:◎(フラット35)、30%まで:○、35%まで:○〜△、40%超:×
・融資比率
80%まで:◎(フラット35)、90%まで:○、95%まで:○〜△、100%超:×
*中古物件などの注意点:物件価格は購入価格ではなく
金融機関の評価価格になります。借り換えや中古物件は要注意
(住宅ローンについて真剣に考えていきたい方、
プロのサポートを受けながら不安解消していきたい方は、
住宅ローンサポートパックの利用をおすすめします)
|